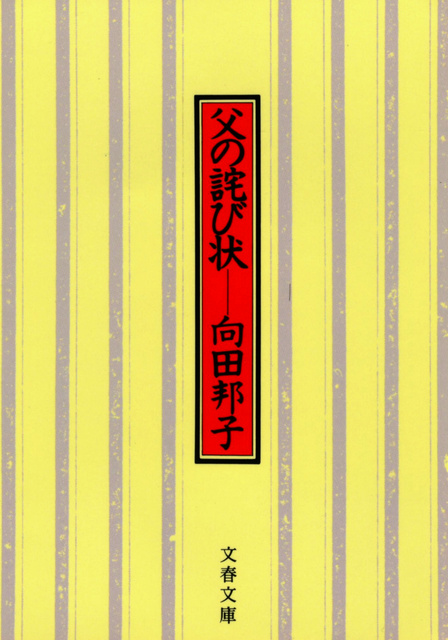この夏、飛行機事故での急逝から40年を迎えた向田邦子さん。昭和の時代に仕事、私生活の両方で華麗に生きた「憧れの女性」は、若い世代からはまた違ったかたちの共感も受けながら愛され続けている。時代を超える生き方と文章の本質とは。
脚本家、作家、エッセイストとして活躍し、51年の生涯を駆け抜けた向田邦子(1929~81)が急逝して40年。その存在は今も色あせない。この夏は雑誌で特集が組まれたり、作品を語り合う読書会が催されたりした。
作品は今なお売れ続ける。昨年3月に出版された『向田邦子ベスト・エッセイ』(筑摩書房)は発行部数が16万部を超えた。同社の担当者は「これだけ時間が経っても関連書籍が出続け、新しい読者をつかみ続ける。そんな作家はほとんどいない」と言う。女性を中心に幅広い世代に購入されており、10~20代の購入者も2割弱いたという。
向田は雑誌編集者などを経てテレビ脚本の道へ。「寺内貫太郎一家」など多くの名作ドラマを生み出す傍ら、妹と小料理屋を開くなど多忙を謳歌(おうか)した。直木賞を受賞した翌年夏、旅先の台湾で飛行機事故に遭い亡くなった。
自らの身辺をつづるエッセーを書くきっかけになったのは、45歳で乳がんを患ったことだった。テレビ関連の仕事を降りて治療にあたっていたころ、都市情報誌「銀座百点」の依頼を受け、76年から2年半にわたって連載した。それをまとめたのが『父の詫び状』だ。あとがきには「誰に宛てるともつかない、のんきな遺言状を書いて置こうかな、という気持」があったとつづっている。
都市情報誌「銀座百点」で1976~78年にかけて連載された随筆24本(表題作を含む)を収録した初のエッセー集。自身の子ども時代の回想を中心に、昭和の家庭や社会の姿を映し出した。86年にはNHKでドラマ化もされた。累計発行部数は約183万部。
表題作「父の詫(わ)び状」は、頂き物の生きた伊勢エビを放し、玄関が汚れてしまったことから、保険会社に勤めていた父親の回想へ。夜に客人を連れて帰宅する権力的な振る舞いに反発しつつ、そうした行動の背後にある父の厳しい幼少期も紹介される。客が酔いつぶれて帰ったある朝、玄関に残った吐瀉(としゃ)物を向田が片付けるのを後ろで見ていた父は素直に謝罪せず、後日、不器用なねぎらいの手紙を寄越してくる――。
身近な出来事から家族で過ご…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル