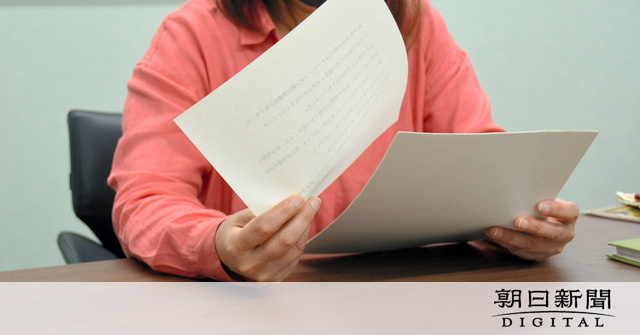
ハンセン病元患者の家族への差別に対する国の責任を認めた熊本地裁の判決から28日で1年を迎える。判決は確定し、昨秋には補償金の支払いを定めた法律もできた。裁判を闘った家族たちを取り巻く状況は変わったのか。
「裁判で終わりじゃない」
家族訴訟で原告の一人だった関東地方の50代女性が、自身の体験を取材に語り始めたのは判決後のことだ。
両親は元患者で、今も療養所にいる。つらい過去に触れたくないし、親族が不利益を被るかもしれないとの恐怖もある。
訴訟では、女性を含むほとんどの原告が差別を恐れて匿名だった。判決から1年たっても、名前や顔を出せる状況にはなっていない。ネットでは、2001年に元患者本人への賠償を国に命じた別の訴訟の判決を引き合いに「また賠償金をもらうのか」などと批判するコメントを目にした。
だからこそ、「裁判で終わりじゃない。話さないと伝わらない。小さなことでもできることをしよう」と心に決めた。昨秋には、差別解消に向けて原告団と国が啓発のあり方を話し合う協議に参加した。
5歳の時、両親と離ればなれに
子どもの頃の記憶をよく思い出せない。「あまり考えないように、無意識に嫌なことにふたをしてきたのかもしれない」
5歳のころ、両親が療養所に隔離され、祖父母のもとに預けられた。会えるのは夏休みか冬休みだけ。授業参観で教室の後ろを振り返っても、その姿はなかった。同級生に神社に呼び出され、「親がいないくせに」と殴られた。友達の父親にも無視された。
両親が恋しくて、よく泣いた。「どうして一緒に暮らせないの」と尋ねても、その理由を誰も教えてくれない。両親がいるのは療養所だと知ったのは20歳ごろ。父は「俺たちのことを聞かれたら、刑務所にいると言え」と語った。
患者の隔離規定が盛り込まれた…
980円で月300本まで2種類の会員記事を読めるシンプルコースのお申し込みはこちら
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル